スポーツ整形について

ケガをしていないのに
なぜか痛みがでてしまう
スポーツでは衝撃による外傷とは別に、繰り返しの動作による負荷で症状が出ることもあります。適切な治療を行わずに無理して運動を続けると、再発する、重症化するなどのリスクがありますので、整形外科で診察を受けられることを推奨します。当院では、試合が近い場合や休めない場合など、患者さんの状況に応じた適切な選択をサポートいたします。

ケガからの競技復帰後
思うように結果がでない
ケガの部分だけ治ったからといって、身体がケガの前の状態に戻るわけではありません。痛みがとれて日常生活が送れることと、スポーツ復帰ができる状態とは、かけ離れています。そもそも、ケガ自体も、起こるべくして起こっている場合があります。スポーツでケガをする原因の多くは体幹バランスの悪さや、部分的な筋力低下です。その場合、ケガの部分だけ治しても、再発してしまいます。ケガをしてしまった人は、なぜこのケガをしてしまったのか医師や理学療法士による分析をして治療する必要があります。
このような症状、
お悩みはご相談ください
- ケガの予防をしたい
- うまく身体が動かない
- パフォーマンスアップししたい
- 膝が痛い
- ケガの後から不調が続いている
- 足の裏が痛い
- 肩が痛い
- 足首を何度も痛める
- 肘が痛い
- 腰が痛い
- 腕が曲がらない
- 身体の柔軟性が低い
- 腕に脱力感がある
当院のスポーツ整形外科

原因検索から再発予防まで
アスリートの身体を
総合的にサポート
当院では、スポーツで生じた痛みの原因検索、動作の確認、早期復帰のためのリハビリ、再発予防の身体作りなどを実施しており、かつ競技特性に必要な身体機能の獲得もサポートさせていただきます。過去、さまざまなお悩みの持つアスリートのかたがたにご相談いただいており、実績も豊富にございますのでご安心ください。
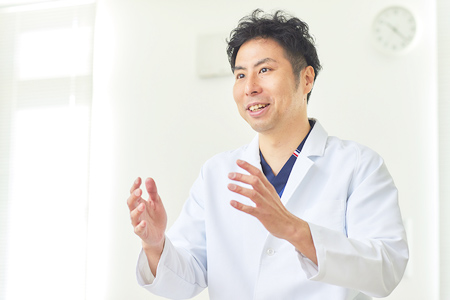
スポーツ関連に特化した医師が在籍
当院の医師は、スポーツ医の資格を取得しています。医師免許とは別に認定される必要があります。医学的診療に加えて運動処方やメディカルチェックも行い、運動するかたを総合的にサポートいたします。

一般のかたからプロアスリートまで
豊富な実績で支える確かな治療
スポーツを愛するすべての方へ適切な治療とリハビリを提供します。これまでに一般のかがからプロアスリートまで、さまざまな競技レベルの患者さんをサポートしてきた豊富な実績があります。ケガの治療だけでなく、競技復帰やパフォーマンス向上を見据えたリハビリにも力を入れ、一人ひとりの目標に寄り添った治療を行っています。スポーツによる痛みや違和感がありましたら、ぜひご相談ください。
スポーツ整形の治療について
その他のスポーツも
お気軽にご相談ください!
※競技特性によりかかる負担が異なるため、競技特性に合わせて丁寧に対応いたします
野球

身体全体をうまく使えず腕の力だけで投げていると、肩や肘に過度な負担がかかって痛めてしまいます。痛みのある状態のまま投球を続けていると、さらに大きなケガに繋がり、長期離脱となる可能性もあります。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- 投球後に肩が重だるい、痛みが出る
- 投球時に肘の内側が痛む
- バットを振ると手首や肘に痛みが走る
- ダッシュやスライディング後に太ももが張る、痛む
- 腰をひねると違和感がある、痛みを感じる
- キャッチングや送球時に指を突き指しやすい
代表的な疾患
- 野球肘
- 中頭疲労骨折
- リトルリーガーズショルダー
- 胸郭出口症候群
- リトルリーガーズエルボー
- 腰椎分離症
- 上腕骨内側上顆障害
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 離断性骨軟骨炎(OCD)
- 膝蓋腱炎
- 上腕骨小頭障害
- 大腿四頭筋腱炎
主な疾患
野球肘|投球動作による肘の障害
投球動作の繰り返しによる肘関節の障害で、特に成長期の選手に多く見られます。内側上顆炎(内側型)、離断性骨軟骨炎(外側型)、疲労骨折などが含まれ、痛みや可動域の制限を引き起こします。初期段階で適切な治療を行わないと、関節の変形や機能障害につながるリスクがあります。フォームの見直しや投球制限の管理、適切なストレッチや筋力トレーニングが予防に重要です。痛みや違和感がありましたら、早めの診察をおすすめします。
腰椎分離症|
繰り返しの負荷による腰の疲労骨折
腰を反る・ひねる動作の繰り返しによって腰椎にストレスがかかり、疲労骨折を引き起こす疾患です。野球では、スイングや投球動作の体幹のひねりが原因となることが多く、成長期の選手に発症しやすい傾向があります。初期の段階では、安静やリハビリによる回復が期待できますが、放置すると分離すべり症へと進行し、慢性的な腰痛につながる可能性があります。体幹の安定性を高めるトレーニングや適切なケアが予防のカギとなります。
サッカー

走り回る際の足首や膝のケガ、キック動作による疲労の蓄積やケガが主な疾患です。キック動作では大きな筋肉の収縮を伴うので、身体の使い方が悪い場合などはリスクが高くなります。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- キック時に股関節の付け根が痛む
- 方向転換時に膝が引っかかるような感じがする
- すねの内側がズキズキ痛む(走ると悪化する)
- シュート後に太ももの裏が突っ張る、痛む
- 足首をひねりやすく、歩くと痛みが残る
- ヘディング後に首が重だるい、動かしにくい
代表的な疾患
- 足関節捻挫
- 膝蓋腱炎
- アキレス腱周囲炎
- シンスプリント
- 肉離れ
- 骨盤剥離骨折
- 腰痛症
- グロインペイン
- オスグット
- 前十字靱帯損傷
- 鵞足炎
- 後十字靱帯損傷
- 大腿四頭筋腱炎
- 内側側副靱帯損傷
- 半月板損傷
- 有痛性外脛骨
- 足底腱膜炎
- シーバー病
- 偏平足
主な疾患
足関節捻挫|
サッカーで最も多い足首のケガ
サッカーの急な方向転換やジャンプの着地、接触プレーなどで足首をひねることで靭帯を損傷する疾患です。軽度の捻挫なら数日で回復しますが、靭帯が伸びたり部分断裂すると腫れや痛みが長引き、歩行にも支障が出ることがあります。適切な治療を行わないと、靭帯が緩み捻挫を繰り返しやすくなるため、早期の固定やリハビリが重要です。ストレッチやバランストレーニングで足首を強化し、予防を心がけましょう。
オスグッド|
成長期に多い膝の痛み
成長期の子どもに発症しやすい膝の障害で、ダッシュやジャンプを繰り返すことで膝の下にある脛骨粗面が炎症を起こし、腫れや痛みを引き起こします。サッカーでは、シュートやダッシュ動作による負担が大きく、症状が悪化すると正座や階段の昇降も困難になることがあります。ストレッチや太ももの筋力強化が予防につながり、痛みが強い場合は運動量の調整が必要です。
シーバー病|
かかとの痛みが特徴の成長期障害
成長期の子どもに多い疾患で、アキレス腱が踵の骨に強い牽引力をかけることでかかとに痛みや腫れを引き起こします。サッカーでは、ダッシュやジャンプの動作が多いため、発症リスクが高くなります。症状が悪化すると運動時だけでなく、歩行時にも痛みが出ることがあるため、早期の対応が重要です。運動後のアイシングや適切なストレッチを行い、足底の負担を軽減することで症状の悪化を防ぐことができます。
ジョギング・ランニング

長距離を走ることで、徐々に膝や足首の痛みが出てしまう患者さんが多くいらっしゃいます。膝周囲の筋力のバランス不良や柔軟性低下、O脚、フォーム不良、足首の硬さなどが原因としてあげられます。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- 長時間走ると膝の外側が痛くなる
- 朝起きて歩き始めると足裏がズキズキする
- ランニング後にすねの内側がジンジン痛む
- 走るとアキレス腱が引っ張られるように痛い
- 長時間走ると股関節の前側が重くなる、痛む
- ランニング後に腰が張る、痛みを感じる
代表的な疾患
- 鵞足炎
- 膝蓋腱炎
- 腸脛靱帯炎(ランナー膝)
- シンスプリント
- 足部伸筋腱炎
- 大腿四頭筋腱炎
- 肉離れ
- 偏平足
- 底腱膜炎
主な疾患
鳶足炎|
膝の内側に痛みが生じるランナーの障害
膝の内側にある鵞足(がそく)と呼ばれる腱が炎症を起こし、膝の内側に痛みや腫れが生じる疾患です。ジョギングやランニングでの過度なトレーニング、筋力不足、ストレッチ不足が原因となりやすく、特に膝を曲げる・伸ばす動作で痛みを感じることが多いです。ウォームアップの徹底やランニングフォームの見直し、内ももや太ももの筋力強化が予防のポイントとなります。痛みを感じたら無理をせず、適切なケアを行いましょう。
偏平足|
ランナーの足にかかる負担を増やす原因
足の土踏まず(アーチ)が低下し、歩行やランニング時に足裏全体で衝撃を受けやすくなる状態です。特にランニングでは、足裏やふくらはぎに過剰な負担がかかりやすく、足底筋膜炎やアキレス腱炎などのリスクが高まります。足の疲労や痛みが出やすく、長時間のランニングが困難になることもあります。適切なインソールの使用や、足底の筋力トレーニングでアーチを支えることで、衝撃を軽減しパフォーマンス向上につながります。
シンスプリント|
すねの内側が痛むランナーの障害
脛(すね)の内側がズキズキ痛む障害で、特にジョギングやランニングの習慣がある人に多く見られます。過度なランニングや硬い地面でのトレーニング、足のアライメント異常が原因となり、脛骨の骨膜に炎症が生じます。初期段階では運動後に痛みを感じますが、進行すると歩行時にも痛みが出ることがあります。ランニングの強度を調整し、適切なシューズ選びやストレッチを行うことで予防が可能です。
ゴルフ

うまく身体を捻ることができずに腰を痛めてしまったり、手打ちになってしまって手を痛めるかたが多く見られます。長く競技を続けるためにも、痛みが生じたら早めに対処しましょう。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- スイング時に腰がピキッと痛む
- クラブを振ると肘の内側が痛い
- スイング後に手首がジンジンする
- 肩を回すと引っかかるような違和感がある
- 長時間プレーすると膝がズキズキ痛む
- 歩行時に股関節がゴリゴリ鳴る、痛む
代表的な疾患
- 母指CM関節症
- 肋骨疲労骨折
- ばね指
- 肩関節周囲炎
- ド・ケルバン腱鞘炎
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 有鉤骨骨折
- 腰痛症
- 上腕骨外側上顆炎
主な疾患
有鉤骨骨折|
ゴルフスイングによる手のひらの負傷
手のひらの小指側にある有鉤骨が折れる疾患で、ゴルフクラブを強く握る動作やダフリ(地面を叩くミスショット)が繰り返されることで発生します。初期症状は手のひらの痛みや握力低下ですが、悪化すると骨片が神経を圧迫し、小指や薬指にしびれが生じることもあります。軽度であれば固定による保存療法で治癒しますが、骨片が離れている場合は手術が必要になることもあるため、早期診断と適切な治療が重要です。
上腕骨外側上顆炎|
ゴルフスイングによる肘の負担
ゴルフスイングの繰り返しによって肘の外側に炎症が起こる疾患です。クラブを強く握る、無理なスイングを続けることで、手首や前腕の筋肉が過度に緊張し、肘に負担がかかります。痛みはクラブを振る動作や物を持ち上げる際に悪化し、放置すると日常生活にも支障をきたすことがあります。予防には、適切なスイングフォームの習得や、ストレッチ、前腕の筋力強化が効果的です。
ラグビー

衝突による偶発的なケガ、スクラムやタックルの繰り返し動作などにより首や腰を痛めてしまう場合があります。柔軟性低下や筋力不足、筋力バランス不良、姿勢不良などがリスクを高める主な原因です。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- タックル後に肩を動かすと痛みがある
- ジャンプ後の着地で膝にズキッとした痛みが走る
- スクラム後に首が重い、動かしにくい
- ダッシュ時にふくらはぎがピリッと痛む
- 試合後に腰が張って動きが鈍くなる
- コンタクトプレー後に足首が腫れている、痛い
代表的な疾患
- 前十字靱帯損傷
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 後十字靱帯損傷
- 頚椎椎間板ヘルニア
- 内側側副靱帯損傷
- 胸郭出口症候群
- 半月板損傷
- グロインペイン
- 腰椎分離症
- 肉離れ
- 肩関節脱臼
主な疾患
肩関節脱臼|
タックルや衝突による肩の外傷
ラグビーのタックルやスクラム時の衝撃、転倒時の手のつき方が原因で肩の関節が外れる障害です。特に前方脱臼が多く、腕を持ち上げたり回すと強い痛みや違和感が生じることが特徴です。一度脱臼すると関節が不安定になり、再発を繰り返す「反復性脱臼」に移行するリスクが高いため、早期の固定とリハビリが重要です。再脱臼を予防するためには、肩周囲の筋力強化や正しいフォームの習得が効果的です。
腰椎椎間板ヘルニア|
スクラムや衝撃で発症する腰の障害
スクラムやタックル時の強い負荷、繰り返しのジャンプやダッシュ動作で腰椎の椎間板が突出し、神経を圧迫する疾患です。主な症状は、腰の痛みや足のしびれ、長時間の立位や前かがみ動作での違和感などがあります。悪化すると歩行やスポーツ復帰が困難になるため、適切なストレッチや体幹トレーニングで腰の安定性を高めることが重要です。症状が強い場合は、薬物療法や手術が検討されることもあります。
バスケットボール

走る、飛ぶ、止まる、切り返すなど動作の多い競技です。身体の使い方が悪い、柔軟性が不足しているなどの要因で下肢や腰部に負担が蓄積する、着地動作などで捻挫や靭帯損傷を生じるリスクがあります。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- ジャンプ後の着地時に膝の下がズキズキ痛む
- 足首をひねりやすく、腫れがなかなか引かない
- 急な方向転換で膝に違和感を感じる
- 試合後に腰が張って前屈がしにくい
- シュート時に肩がゴリゴリする、痛む
- リバウンド時に指を突き指しやすい
代表的な疾患
- ジャンパー膝
- 足関節捻挫
- オスグット
- 前十字靱帯損傷
- 膝蓋腱炎
- 半月板損傷
- シンスプリント
- 肉離れ
主な疾患
足関節捻挫|
ジャンプや急な動きによる足首の負傷
バスケットボールのジャンプの着地や急な方向転換、相手との接触時に足首をひねることで発生する障害です。特に外側靭帯の損傷が多く、軽度では腫れや痛みのみですが、重度になると靭帯が部分または完全に断裂し、歩行困難や慢性的な不安定感が生じることもあります。適切な固定とリハビリを行わないと、再発を繰り返しやすくなるため、足首の安定性を高める筋力トレーニングが予防に重要です。
前十字靭帯損傷|
急なストップや方向転換で発生する膝の大ケガ
シュートやディフェンス時の急なストップ動作、ジャンプの着地、相手との接触で膝に強い負荷がかかることで発生します。損傷時には膝が「バキッ」と鳴ることがあり、痛みとともに膝の不安定感が強くなるのが特徴です。一度断裂すると自然治癒は難しく、手術が必要になるケースも多いため、早期診断と適切なリハビリが重要です。予防には、太ももやハムストリングスの筋力強化、ジャンプや着地動作の改善が効果的です。
バレーボール

飛んで着地するために下肢を動かし、スパイクを打つ際に体幹と肩を使います。筋力不足や下肢の柔軟性低下が原因で負荷が蓄積し、肩や背中、腰の痛みを生じてしまうことが多い競技です。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- ジャンプ後の着地時に膝の下がズキズキ痛む
- 足首をひねりやすく、腫れがなかなか引かない
- 急な方向転換で膝に違和感を感じる
- 試合後に腰が張って前屈がしにくい
- シュート時に肩がゴリゴリする、痛む
- リバウンド時に指を突き指しやすい
代表的な疾患
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 肉離れ
- 腰椎分離症
- シンスプリント
- 肩関節周囲炎
- オスグットシュラッター病
- グロインペイン
- ジャンパー膝
- 足関節捻挫
- 膝蓋腱炎
主な疾患
腰椎分離症|
スパイクやジャンプ動作の繰り返しによる腰の障害
スパイクやブロックなどのジャンプ動作、着地時の衝撃、腰を大きく反らす動作が繰り返されることで発生する疲労骨折です。特に成長期の選手に多く、腰の痛みや動きの制限が主な症状です。初期の段階で適切な治療を行えば安静やリハビリで改善することが多いですが、進行すると分離すべり症に移行し、慢性的な腰痛の原因となることもあります。予防には、体幹の安定性を高める筋力トレーニングや柔軟性を向上させるストレッチが効果的です。
肩関節周囲炎|
スパイクやサーブの繰り返しによる肩の炎症
スパイクやサーブなどのオーバーヘッド動作を繰り返すことで、肩関節周囲の腱や靭帯に炎症が生じる疾患です。肩を上げたり、回す際に痛みを感じることが多く、症状が進行すると腕をスムーズに動かせなくなることもあります。放置すると慢性化し、パフォーマンスの低下につながるため、早期のストレッチやアイシング、肩周りの筋力強化が重要です。痛みが続く場合は、理学療法や適切な治療を受けることをおすすめします。
バレエ

つま先立ちの繰り返しにより、足の指や足首に負担がかかります。また、美しい姿勢を意識して無理に背中を反ることで、背中や腰に負担が蓄積して痛みを発症することがあります。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- ジャンプ後の着地時に膝の下がズキズキ痛む
- 足首をひねりやすく、腫れがなかなか引かな
- 急な方向転換で膝に違和感を感じる
- 演技後に腰が張って前屈がしにくい
代表的な疾患
- 外反母趾
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 変形性関節症
- 腰痛症
- 開張足
- 肉離れ
- アキレス腱周囲炎
- 反り腰
主な疾患
外反母趾|
ポワントやターン動作による足の変形
足の親指が小指側に曲がり、関節部分が突出して痛みや炎症を引き起こす疾患です。バレエでは、ポワント(つま先立ち)やターン動作によって足の指に強い負荷がかかるため、靴の圧迫と過度なストレスが原因で発症しやすい傾向があります。痛みが進行すると、日常生活にも支障をきたすため、適切なシューズの選択や足のアーチを支えるトレーニング、ストレッチが予防に効果的です。重度の場合は、装具療法や手術が必要になることもあります。
腰椎症|
反り腰姿勢が引き起こす慢性的な腰の痛み
腰椎の椎間板や椎体に負担がかかり、変性が進行することで痛みや動作制限が生じる疾患です。バレエでは、アラベスクやカンブレなどの動作で腰を大きく反らせることが多く、過度な負荷が繰り返しかかることで発症しやすくなります。初期段階では軽い違和感や疲労感が中心ですが、進行すると慢性的な痛みや神経症状を伴うこともあります。体幹を強化し、正しい姿勢で踊ることが腰椎への負担を軽減し、予防につながります。
テニス

前後左右に動き回る際に膝や足首を痛めたり、ラケットを振る動作の負担の蓄積によって、手首、肘、肩、背中などに痛みが生じることがあります。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- ジャンプ後の着地時に膝の下がズキズキ痛む
- 足首をひねりやすく、腫れがなかなか引かない
- 急な方向転換で膝に違和感を感じる
- 試合後に腰が張って前屈がしにくい
- スマッシュ時に肩がゴリゴリする、痛む
代表的な疾患
- 足関節捻挫
- 胸郭出口症候群
- アキレス腱周囲炎
- 腰痛症
- 肉離れ
- オスグット
- 腱鞘炎
- 鵞足炎
- 上腕骨外側上顆炎
- 大腿四頭筋腱炎
- 肩関節周囲炎
主な疾患
上腕骨外側上顆炎|
ラケットの振りすぎによる肘の痛み
ラケットを振る際に手首や前腕の筋肉が過剰に使われることで、肘の外側に炎症が起こる疾患です。特にバックハンドストロークを繰り返すことで負担が蓄積し、肘の外側に痛みが生じ、握力の低下や物を持つ際の痛みにつながることがあります。悪化すると日常生活にも支障をきたすため、適切なフォームの習得、ストレッチ、筋力トレーニングが予防に効果的です。症状が進行する前に、早めのケアを行いましょう。
肩関節周囲炎|
サーブやスマッシュによる肩の負担
サーブやスマッシュの動作を繰り返すことで肩の腱や靭帯が炎症を起こし、痛みや可動域の制限が生じる疾患です。特にオーバーヘッド動作が多いテニスでは、肩への負荷が大きく、インピンジメント症候群などの原因にもなります。症状が悪化すると腕がスムーズに上がらなくなり、プレーに影響を及ぼすこともあります。肩周囲のストレッチや筋力トレーニング、適切なアイシングを行い、炎症を予防することが重要です。
陸上

ダッシュや長距離走の繰り返しで膝やすねに負担がかかり、シンスプリントやランナー膝を引き起こすことがあります。跳躍種目では踏切や着地時の衝撃で股関節・膝・足首を痛めやすく、投擲では肩や肘に繰り返しの負担がかかることで痛みが生じることがあります。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- スタートダッシュで太ももの裏がピリッと痛む
- 長時間走ると膝の外側が痛くなる
- 踏切動作で股関節が詰まるような感じがする
- 走るとすねの内側がジンジン痛む
- トラックを回ると足首に違和感がある
- 腰に負担がかかり、後半になると痛みが増す
代表的な疾患
- 腸脛靭帯炎(ランナー膝)
- 半月板損傷
- 脛骨過労性骨膜炎
- 疲労骨折
- 足底筋膜炎
- 股関節インピンジメント症候群
- アキレス腱炎
- 腰椎分離症
- 前十字靭帯損傷
- 肉離れ
主な疾患
腸脛靭帯炎(ランナー膝)|
膝の外側が痛むランナーの障害
ランニングやジャンプの繰り返しにより、膝の外側にある腸脛靭帯が大腿骨と擦れて炎症を起こす疾患です。特に長距離ランナーや下り坂を走る際に発症しやすく、初期は運動時のみの痛みですが、進行すると歩行時にも違和感が生じることがあります。予防には股関節周囲や太もものストレッチ、適切なフォームの習得が重要です。痛みを感じたら無理をせず、アイシングやリハビリで早期回復を目指しましょう。
アキレス腱炎|
ランニング時のかかと周辺の痛み
ランニングやジャンプの繰り返しによってアキレス腱に過度な負担がかかり、炎症や痛みを引き起こす疾患です。特に長時間の走行や、硬い路面でのランニングが原因となりやすく、かかとの上部に腫れや圧痛が生じることがあります。放置するとアキレス腱の断裂につながる可能性もあるため、適切なストレッチ、ふくらはぎの筋力強化、衝撃吸収性の高いシューズの選択が予防に有効です。早期のケアで長期間の離脱を防ぎましょう。
ハンドボール・水球

投球動作の繰り返しで肩や肘に強い負担がかかります。特に水球は水の抵抗も加わり、肩の障害が起こりやすい競技です。ハンドボールでは、ジャンプや方向転換で膝や足首をひねりやすく、靭帯損傷や半月板損傷につながることがあります。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- ジャンプ後の着地時に膝の下がズキズキ痛む
- 足首をひねりやすく、腫れがなかなか引かない
- 急な方向転換で膝に違和感を感じる
- 試合後に腰が張って前屈がしにくい
- シュート時に肩がゴリゴリする、痛む
- リバウンド時に指を突き指しやすい
代表的な疾患
- 半月板損傷
- 前十字靭帯損傷
- 足関節捻挫(靭帯損傷)
- 股関節インピンジメント症候群
- 脳振盪(軽度外傷性脳損傷)
主な疾患
腰椎分離症|
繰り返しのジャンプや回旋動作による腰の疲労骨折
ジャンプやスロー動作の繰り返しで腰椎に負担がかかり、疲労骨折を引き起こす疾患です。ハンドボールではシュートやジャンプの着地時、水球では水中でのダイナミックな動きや回旋動作が原因となりやすい 傾向があります。初期の段階で適切な治療を行えば安静やリハビリで回復できますが、進行すると慢性的な腰痛につながることもあります。予防には体幹の強化やストレッチ、適切なフォームの習得が重要です。
肩関節周囲炎|
投球動作の繰り返しによる肩の炎症
ハンドボールや水球のスロー動作を繰り返すことで、肩の腱や靭帯に炎症が生じ、痛みや可動域の制限が起こる疾患です。特に水球は水の抵抗が加わるため、肩への負担が大きく、炎症が慢性化しやすい 傾向があります。症状が悪化すると、肩がスムーズに動かなくなり、パフォーマンスの低下につながることもあります。ストレッチや筋力強化、適切なフォームの習得が予防と早期回復に効果的です。
ダンス

つま先立ちやジャンプの衝撃で足首や膝に負担がかかります。ターンや開脚の繰り返しで股関節を痛めたり、腰を反る動作で腰椎分離症のリスクも。リフトを伴う動作では、肩の不安定性や負傷に注意が必要です。
このような症状で
お悩みではありませんか?
- ターン時に足首がぐらつく、痛む
- ジャンプの着地で膝がズキッとする
- 開脚すると股関節が詰まるような感じがある
- 腰を大きく反ると痛みが走る
- 踊り終わった後にアキレス腱が張っている
- リフト後に肩が重く、痛みを感じる
代表的な疾患
- 足関節捻挫(靭帯損傷)
- 股関節唇損傷
- 前十字靭帯損傷
- 腰椎分離症
- 腰痛症
- 脛骨疲労骨折
- 足底筋膜炎
- 外反母趾・ハンマートゥ
- ジャンパー膝(膝蓋腱炎)
- 肩関節不安定症
主な疾患
前十字靭帯損傷|
ジャンプやターン時の膝への負担による損傷
ジャンプの着地やターン時の膝のひねり、急な方向転換の際に膝に強い負荷がかかることで発生する疾患です。ダンスでは、特にバレエやジャズダンス、ヒップホップなどでジャンプやピルエット(回転動作)を多用するため、着地時に膝が内側に入る動きが原因で靭帯が断裂しやすくなります。損傷すると膝の不安定感や強い痛みがあり、手術が必要になることもあります。予防には太ももや体幹の筋力強化、正しい着地動作の習得が重要 です。
腰椎症|
過度な反り腰姿勢が引き起こす慢性的な腰痛
腰椎の椎間板や椎体に負担がかかり、変性が進行することで痛みや可動域の制限が生じる疾患です。ダンスでは、アラベスクやカンブレなどの腰を反る動作や、長時間の不安定な姿勢が原因となりやすく、慢性的な腰痛や神経症状を引き起こすことがあります。特に、柔軟性が高いダンサーほど関節に負担がかかりやすいため、体幹の安定性を高めるトレーニングや正しい姿勢の習得が重要です。症状が悪化する前に適切なケアを行いましょう。
