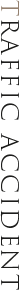
安心の
交通事故治療の
ポイント
日本整形外科学会
専門医の診断と治療
理学療法士の
マンツーマンリハビリ
弁護士連携&紹介
交通事故患者の
豊富な経験と対応力
院長からのメッセージ

交通事故に遭ってしまったらお早めに
整形外科への通院を開始してください
交通事故での症状は、早期に治療開始するほど後遺症を残しにくくなります。事故後時間が経過してから受診すると、事故との関連性が証明できないケースもございますので、自動車保険で治療費を請求できないリスクがあります。 当院では交通事故に遭われたかたに対して、投薬治療だけではなく、メンタルケアから理学療法士によるリハビリテーションなど、患者様一人ひとりの症状に合わせた治療を提供しています。 交通事故によるむち打ち症や痛みなどの症状は数日後から痛みが現れたり、思ったよりも治療が長引いたりすることがあります。早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。特に交通事故での症状は早期に治療開始するほど後遺症を残しにくくなります。交通事故に遭ったらお早めに整形外科への通院を開始することをおすすめします。
交通事故について

交通事故でのむち打ちは
早期治療が重要な疾患です
交通事故後の代表的な疾患に、むち打ち症があります。首(頸部)にはたくさんの神経が通っているため、痛めてしまうとさまざまな症状が現れることがあります。放置すると首を庇い姿勢が悪化して、痛みが強くなるという悪循環に陥るリスクもあります。当院では早期回復を目指すために痛みを抑える治療、姿勢や筋肉の緊張を改善するリハビリテーションを行い、患者さんの状態に合わせた総合的な治療を行います。
このような症状、
お悩みはご相談ください
- 首の痛み
- 手足のしびれ
- 筋肉の張り
- 吐き気
- 頭痛
- めまい
- 首が回らない
- 目のかすみ
- 耳鳴り
- 疲労感
当院の交通事故治療

治療や個別リハビリなど充実の体制
当院には、豊富な臨床経験と知識を持つ日本整形外科学会整形外科専門医が在籍しています。問診・診察、レントゲンや超音波検査など必要な検査を行い、土浦協同病院と連携して治療を進めます。また、リバビリの際は、国家資格を持った理学療法士による個別リハビリに対応しています。患者さん一人ひとりの状態に適した内容をご提供し、日常生活での注意点なども合わせてご説明させていただきます。

豊富な対応実績や
弁護士との連携など
患者さんが安心できる環境
多くの交通事故患者に対応してきた当院では、医師の指示・監視下のもと、薬物治療や運動療法、物理療法を組み合わせて治療を行います。後遺障害診断書の作成も可能ですので、お気軽にご相談ください。また当院は、弁護士との連携体制も整えております。患者さんの状況をお伺いして、適宜ご紹介させていただきます。
治療について
診察・検査

医師が診察を行い、必要に応じてレントゲンや超音波検査などの診断を行います。交通事故での症状は画像診断のみでは判別できないことがありますので、動作分析や姿勢異常なども含めて判断し、治療方針をご提案いたします。
リハビリテーション

疼痛のある部位をどの程度まで動かして良いのか、日常生活での注意点、自宅でのストレッチ方法など、患者さん一人ひとりに合わせた治療プランを理学療法士からご説明いたします。
物理療法

患部の組織に対して、専用設備を用いて熱や電気などのエネルギーを与える治療方法です。温熱療法、電気療法、牽引療法など、患者さんの症状に合わせて各種物理療法機器を使用して治療します。
交通事故後の通院について

交通事故に遭われた後は
お早めの手続きを推奨いたします
交通事故後に受診する際、手続きの注意点として自賠責保険と治療費の立替えがあげられます。事故時に保険会社との連絡が遅れてしまうと、一時的に患者さんが治療費全額を立替る必要が出てしまいます。最終的な支払額は0円となりますが、一時的なご負担は大きくなりますので、お早めの手続きを推奨しています。
受診の流れ
1 警察へ届け出
交通事故後に警察への報告がない場合、自動車保険を請求する際に必要書類である「事故証明書」の交付が受けられなくなります。交通事故に遭われたらすぐに警察に届出をしましょう。
2 保険会社連絡
相手のある交通事故で被害者である場合は自動車保険会社を通して手続きをすることで、自賠責保険などを適用し、自身の治療費のご負担なく、治療を受けることができます。来院前や来院中に保険会社から当院に連絡があれば、初診からお支払いなく治療開始が可能です。なお、保険会社から連絡が来ていない段階で来院された場合は一度立て替え払いをいただき、後日保険会社から連絡が来たら返金させていただきます。
第三者(自分以外の人)による負傷の治療の場合、公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合 など)で治療を受けることも可能です。その場合、上記の公的医療保険当局に「第三者行為の届け出」が必要になります。詳細は本ページ下部のQ&Aをご覧ください。
通勤途中や業務中に交通事故に遭われた場合は、健康保険証が使用できないため労災保険も選択肢になります。自賠責保険を優先して適用されることが多いですがケースバイケースなので、職場への報告とともに、自動車保険会社にご相談ください。自賠責保険が適用されない場合は、労災保険を適用することになります。
3 早めの受診と継続した通院
事故後はさまざまな症状が出るリスクがありますので、お早めにご来院ください。事故に遭ってから時間が経ってしまうと、症状と事故の因果関係が証明しづらくなるケースがあります。
4 検査・治療
必要に応じて検査を実施して疾患を特定し、適切な治療を受けましょう。早期治療が回復に良い影響を与えます。
交通事故の治療費について

交通事故関連の治療費は
自賠責保険などで支払われます
交通事故で負傷した際の治療における治療費は、加害者の加入している自賠責保険などで支払われます。基本的には患者さんへのご負担はありません。自賠責保険は車に乗るすべてのかたが入ることが義務付けられている保険です。 ※相手が自賠責保険に加入していても、任意保険は加入していない場合には、一旦被害者に負担が生じることなどがございます。詳細につきましては、弁護士にご相談ください。
よくあるご質問

症状がない場合や軽度でも、すぐに病院を受診した方が良いのでしょうか?

すぐに病院を受診しましょう。事故直後は、興奮しているので症状が感じにくいですが、事故後しばらく経ってから症状が強くなる場合もあります。事故直後は症状がないため病院に行かず、後から症状が出て受診しても、事故との関連性を保険会社に疑われる可能性もあります。

どのぐらいの頻度で病院に通院したら良いでしょうか?

症状があるうちは、週2回以上、継続的に病院に通院しましょう。その後は医師と相談しながら、必要に応じて通院します。

整骨院での加療と併用は可能ですか?

当院では整骨院での加療はおすすめしておりません。整骨院での施術や通院は、医学的な必要性に欠けるとみなされることがあり、慰謝料の減額や医療費打ち切りのリスクがあります。また、後遺障害診断書の発行もできません。

整形外科と治療院(整骨院・接骨院)の違いは何ですか?

整形外科には医師と理学療法士が在籍しており、各種検査や医学的な診断、薬の処方、診断書の作成が可能です。この点が治療院との違いです。

どれくらい治療費がかかりますか?

自賠責保険による補償となりますので、基本的には患者さんに負担はありません。ただし、過失割合が高い場合や保険会社に連絡が取れていない場合は治療費が発生することがあります。

治療期間はどれくらいですか?

症状によって異なりますが、むちうち症は3~6ヵ月が基本的な治療期間になります。早期の段階でリハビリ治療に通うことで、その後の治療成績に良い影響を与えることが期待できます。

治療にはどのような保険が使えますか?

基本的には、自賠責保険と健康保険があります。一般的には自賠責保険による治療を行いますが、保険会社と協議し、健康保険を使われて治療する場合があります。健康保険で治療を行う場合は、患者さんが「第三者行為による届け出」を提出する必要があります。

第三者行為とは何ですか?

第三者(自分以外の人)による負傷のことを指します。例えば、対人の交通事故、不当な暴力によるケガ、他人の飼い犬に噛まれたなどがあげられます。このような場合に保険証を用いて治療を受ける場合、公的医療保険当局に「第三者行為による傷病届」一式の提出が必要となります。

今、かかっている医療機関から変えたいです

医療機関は患者さんの意思で自由に変えられます。変更をご希望の場合は保険会社に連絡し、その旨をお伝えください。

通院の途中で保険会社から治療費支払いの打ち切りを判断されたらどうしたら良いでしょうか?

治療の必要性は医師の判断が尊重されるため、保険会社が決めるものではありません。治療費打ち切りの打診があった場合、まずは医師に治療を続けるべきか相談しましょう。

通院の途中で保険会社から症状固定による後遺症診断書の作成をすすめられたらどうしたら良いでしょうか?

症状固定時期は患者と医師が相談しながら決めるものであるため、まずは医師に相談しましょう。

むちうちで可能性のある後遺障害はどのようなものですか?

むちうちは、後遺障害14級9号または12級13号を満たす状況の場合、後遺障害認定される可能性があります。詳しくは医師までご相談ください。

なぜ弁護士さんにも相談した方が良いのでしょうか?

慰謝料の増額、保険会社とのやり取りの委託、治療費打ち切りへの対応、適切な後遺障害等級認定の取得などの理由より、弁護士への相談を推奨しています。
